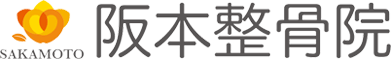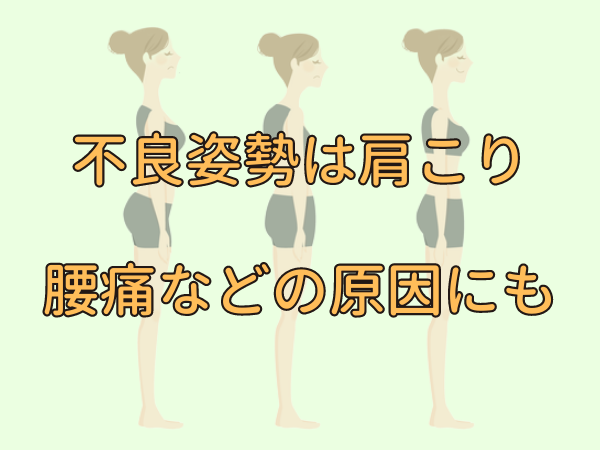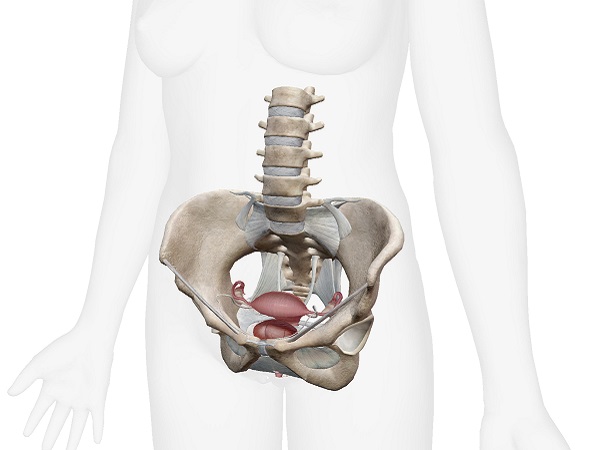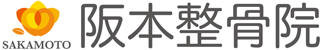昨日はだんじり祭りの試験曳きでした
暑くて熱中症の子も何人か出ていました
今年は涼しくなるのが早いからマシかな・・・と思っていましたが
まだまだ油断ならないですね
さて、前回のブログ内容から聞かれたことがあったのでその事について少し・・・
ストライダーは2〜5歳のバランス感覚などの神経系の発達を促す
ということがウリになっているようです
その根拠の元はおそらくスキャモンの発育曲線というもので
子供の肉体や神経、リンパ、生殖などがどのように発育していくかというグラフです
ここでこのグラフの細かい説明はあえてやめにしますので
知りたい方はググッてくださいね
ここでフォーカスするのは神経系です
神経系は確かに5歳まででおよそ8割方ができるということになります
つまり、、、
この段階で様々な刺激を与えるといいという事です
ストライダーで刺激になるのは
歩いたり、走ったり、木や遊具によじ登ったりするときのバランスとはまた違い
あくまで「自転車に乗る」ためのものです
よく「自転車に早く乗れるようにするため」と聞きますが
何のためにでしょう?
親が楽をするためでしょうか??
いやいや子供のために!
というそこのお母さん!
それって親のエゴになったりしてませんか??
とりあえず読んでご参考にしていただければと思います
まずはじめに
人間はもともと2本足で歩く、走るように体の構造が進化してきました
自転車に乗るのに適した進化はしていません
前回も書きましたが、ちゃんと歩けないのにそんなもんに乗せてどーする?
というのが、私の意見です
それよりもこの神経が発育する段階で
公園を走り回り、遊具によじ登ったり自由な動きで全身の神経に刺激を与える
そしてしっかりした歩き方や、手足の使い方を学ぶ事の方が
よほど発育には適していると思います
たまに
野球させるとすごくうまいけど、マット運動がへた・・・というような子がいます
こうした子はどこかのレベルでまず壁に当たります
体のコントロールがうまくできないことで、もうひとつ上のレベルに行けない要因になりえます
それどころか怪我の素因になることもあります
つまり
自由に動かせる体なくして、日常生活やスポーツなどの運動をうまくできるはずがありません
年配の方や幼児がよく転ぶのは
「体を思うように動かせないから」という理由です
だから
そうした十分に全身の神経を刺激することを経たあとに自転車に乗る・・・
それでも全然遅くないはずです
むしろその方が体の使い方がわかっているので、早く乗れるんじゃないかと思ったりします
また、そうした基礎的な部分が弱いがゆえに
怪我をしやすくなってしまったり
それだけではなく、その子の老後に影響を及ぼすこともありえます
実際、学校で子供の運動器検診が今年から始まりました
よく言われる事で
「しっかりハイハイしないといけない」というものがありますが
それは「発達に必要な過程はしっかりやらなくてはいけない」ということ
(ハイハイでは特に体幹部が関与します)
子供の成長スピードは人それぞれです
あせらず見守ってやるということが大切だと思います